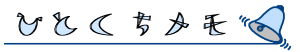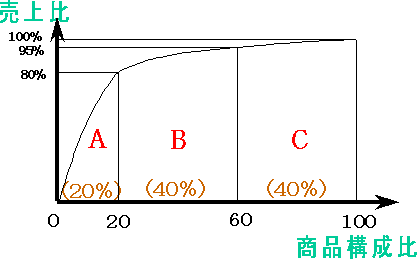 |
|
この原則は、どの会社にも当てはまる。ただし、会社によっては、上位20%のエリート商品で、全売上の90%ぐらいいってしまう会社と、60%ぐらいしかしかない会社とがある。しかし、いずれにしても、わずかな商品で、わが社の売上の半分以上いってしまうという原則に変わりはない。
特許戦略の評価とABC分析 特許戦略の善し悪しは、Aグループの商品に特許が集中しているかどうかできまる。
- 将来をテーマにする特許戦略を、なぜ、現在の売上高分析であるABC分析で評価しなければならないのか。
- 会社の現在の姿は、2~3年前に目指した目標(戦略)の結果である。
- もし、Aグループのエリート商品に特許が集中していなければ、その過去の戦略が誤っていたことになる。
いずれにしても、現在という切り口でとらえたとき、いつも、Aグループの商品に注目せざるを得ない。 - Aグループのエリート商品に特許が集中していなければ、それが結果論であろうとも、特許戦略としては、間違っていたといわざるを得ない。
ABC分析と特許戦略の立案 既に商品化させているものについての改良特許は、Aグループのエリート商品に重点を置くべきものである。
- 既に商品化されているものについての改良特許は、絶対に売れ筋商品であるAグループの商品に集中すべきである。
- ただし、この場合に注意すべきは、このエリート商品の商品寿命である。近い将来引退しなければならないロートルなのか。10年以上も活躍が期待できる若きエースなのか。
もし商品寿命を評価できないなら、若きエースとして扱うべきである。 - Cグループの商品に特許をとる必要など全くない。
- Bグループの商品に関しては、ケースバイケースで決めざるを得ない。