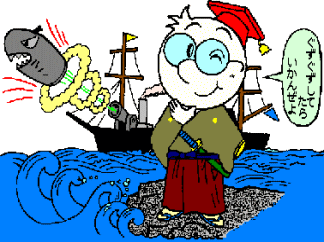2.世界の人々へ、誤解なく伝えるには「論理力」が求められる
確かに日本語は「情感」の表現には向いているが「論理的表現」には向いていない。しかし、問題がここにあり、それを解決するためには、このようにしなければならない、そのためにはこのような努力が必要である、等々を説得し、理解を求めるためには、論理的に筋道を立てなければならない。
論理的思考の起点は、事実の把握を出発点とする。いま生じていることは過去に生じた何らかの結果である。過去を知らずして状況把握は行えない。当然、分析も行えない。分析ができなければ問題点も出てこない。問題点が見つけられなければ、対策も考えられない。あるいは考える必要はない。
つまり「論理力」は、事実を矛盾なく明確に伝えることが目的である。文才は必要ない。要するに日本文化に根ざした叙情的で美しい、あるいは阿吽の呼吸を期待した以心伝心の「文化日本語」でなく、世界へ「物、事、考え」を伝える為の「やさしい平明な日本語」、即ち第二母語としてのもう一つの言語、つまり「文明日本語」を持てば済むことである。
[余計な能書き]:新しい「モノづくり」の時代,“なぜ”を追求し、そして“どうする”を模索する“問答力”が、益々重要となってくる。企業であれば現場だけでなく経営陣も自社商品がどのような技術で構成されているのかを知っておくことは当然の義務である。この、「なぜ、どうする」の力が弱いと全てが後手、後手に回ることになる。
長きに渡る日本の教育政策のおかげか、この「なぜ・どうする」を問い、思考(模索)する能力は、日本人の中で見事なほどに低下している気がする。例えば日本の超エリート集団であるべき政府及び霞が関の施策、何かあった時の対応を見れば、問題の本質をおざなりにして甚だ場当たり的で、曖昧である。これでは世界のエリート連中とは戦えない。
もちろん日本でエリートと呼ばれている人達は、頭脳明晰で語学力もある。しかし自分の考えを相手に認めさせる議論は苦手としている。“そこまで言わなくても理解して欲しい”という阿吽の呼吸は通じない。議論に負けない論理力を持たないと世界のエリート達から認められない。彼らから認められたら“名こそ惜しけれ日本の美”の精神を失わず対峙して行くことで更なる新しい信頼関係が生まれるはずだ。
3,〆は、篠原ブログ79:「名こそ惜しけれ」日本人の美学の核
若いころ、ヨーロッパで、宗教とはいったい何なのかを考えさせられた。“お前は日本人だから仏教徒か”との質問に、仏教の教えに接したこともない存在としては、「ノー」と答えざるをえない。しからば無神論者なのか、と聞かれると、神がいるとかいないとかの話には答えようもない。問いかけてくる相手も私という存在をどのような範疇に当てはめているのかわからなくなる。なぜそのような「些細」なことに拘るのかとこれまた西欧人の考えに理解が及ばない。
キリスト教を信じる彼らにとって、信じる宗教を持たない人間は野蛮人であるか、あるいは得体の知れない存在とみなすということは、既にいくつもの書物で承知はしていたが、自分はなぜそうなのか、宗教なしでも別に何の支障もないことを適確に表現することはできなかったし、彼らがなぜ宗教なしの人間を理解する基礎を持っていないのか、理解できなかった。
後になって、司馬遼太郎さんの本を読むことで、問題のひとつは解決した。司馬さんがどのように記述されていたか、確かではないが、宗教は獰猛な人間を飼いならすために必要とされるという言に出会って、霧が晴れた。彼らには宗教が必要であり、自分たちが必要としているから、相手も必要としているに違いないとする。だから宗教を持たない存在は、自分たちが宗教を持たなかった時の状態と同じく「野蛮」であり、だからこの「福音」を伝授したいという、お節介になるわけだ。
ところが、日本人は、宗教なしでも別に獰猛でもなく、野蛮でもなく、近代文明も受け入れているし、知識教養も高く、礼儀も正しい。いったいどうなっているのだ、ということになる。ここまで書いてきたようにこの疑問に当時は、私は答えられなかったのだが、今ならできる。われわれ日本人は、人間存在の基盤に、「名こそ惜しけれ」という美学を持っているからこそ、キリスト教を信じる西欧人や、そのほかユダヤ教、イスラム教、ヒンヅー教等を信ずるどのような人々に対しても、同じ土俵で毅然と相対(あいたい)することができるのだ。
「名こそ惜しけれ」とは、いうまでもなく坂東武者の中に育った「美学」であり、生きるうえでの基本基準とでもいうべきものである。もちろん宗教ではなく、また哲学という概念にもあわない。この概念を定義するのは難しいので、私はこれを「美学」と呼んでいる。生きるうえでの、美意識に関する感性に基づく、基本的な姿勢とでもいっておく。
鎌倉時代から、現日本の原型は形作られたのだから、その社会におけるエリート層の武士の美学は次第に日本人全体のものとなっていく。「名こそ惜しけれ」自分の行うことには自分が責任を持つ、ということである。恥ずかしい仕事はできないということである。自分の名にかけて、物事はキチンとやるという自意識を高く持った誇り高い存在を支えている美意識なのだ。
農民が作る農産物、職人が作る制作品、これらを見れば、日本人は庶民の隅々までこの「名こそ惜しけれ」の美学を持っていたことがわかる。日系移民という、高等教育を受けたわけでもなく、熱烈な仏教徒でもない普通の民衆が海外の地であれほどの評価を得たのも、この美学が根底にあったからに違いないと私は確信している。
この美学は、戦後、高い品質の工業製品を生み出す原動力にもなった。工場の現場の一人一人が無意識であってもこの美学を持っていたがために、自分が関係した製品は、恥ずかしくないものを市場に出すのだという信念があった。今もあるはずだ。
今なら私は、外国の人々に説明できる。俺たちには「名こそ惜しけれ」の美学があるから、宗教はなくとも、まともな行動が取れ、まともな社会を経営することができるのだと。ただし、外国語で、このことを説明するのは相当に難しい。あれやこれやの実例を示しながら説明していかないと、理解を得るのは大変な作業となるだろう。
ともあれ、われわれ日本人がこの「名こそ惜しけれ」を忘れない限り、というより、まだ維持している人々が先頭に立って行動すれば、21世紀のこれからの困難な局面において、世界のパスファインダー(pathfinders)として尊敬を受け、世界の存続に貢献できることになるだろう。論理の展開の根底にはまともな哲学、人間とは何、どうあらねばならないかの原理原則がなければならず、幸いなことにわれわれはその原理を「名こそ惜しけれ」という一言で表現されるもので持っている。
(2006/01/01 篠原泰正)