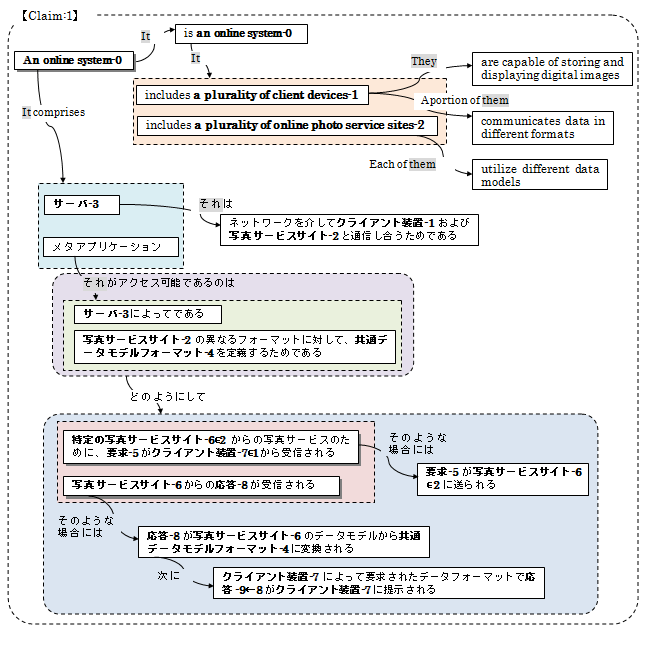構造化クレームを用いた請求項文の作成と翻訳
IPMA >> 構造化クレームを用いた請求項文の作成と翻訳
構造化クレームとは
「構造化クレーム」は、【特許請求の範囲】を設計し、制作し、翻訳し、改訂し、管理する一連の作業を強力に支援する新たなパテントマップです。構造化クレームは、知財専門家同士、あるいは、クライアントと知財専門家との間の強力なコミュニケーション・ツールとなり、戦える特許文書を効率良く作成し、効果的に維持・管理できるようにしてくれます。
構造化クレームは、ISeC(特定非営利活動法人セマンティック・コンピューティング研究開発機構)が策定を進めている「構造化言語」を請求項文に応用したものです。構造化クレームの基本構想は、Japio(一般財団法人日本特許情報機構)特許情報研究所の平成24年度特許版・産業日本語委員会報告書(平成25年3月)にまとめられています。IPMA(知財マネジメント経営を考える会)は、この基本構想に知財現場で得られた蓄積を加味し、構造化クレームを知財経営実務のコミュニケーション・ツールとして活用していきます。(横井)
ここでは図式化のサンプルを一部抜粋しています(詳細説明は、こちらへ)
「構造化クレーム」が果たす役割
自分が発明した特許明細書を作成してくれた弁理士さんのクレームを図式化することで「発明の本質、バリエーションを増やしてくれた箇所、漏れや不足の箇所、不整合や不明瞭な箇所」などが明確になります。それは発明者が書く発明提案書の質をあげることへ繋がります。発明提案書すら用意されていない、あるいは用意されていても不十分な発明提案書では質の良い特許明細書は作れません。弁理士の個人技でゼロから作り上げるのではなく、60~70レベルまでの発明提案書ができていれば“世界で通用する特許明細書”を作ることが可能となります。弁理士の労力も格段と軽くなり品質も安定してきます。弁理士は発明者のチエックが受けられる道具を用意して打ち合わせを重ねれば仕事の質が上げられます。その道具が「構造化クレーム」です。発明者も、知財部も、弁理士も、審査官も、関係者みなさんが「共有」してハピーになりたいものです。
A.2 基本パターンを詳細化する
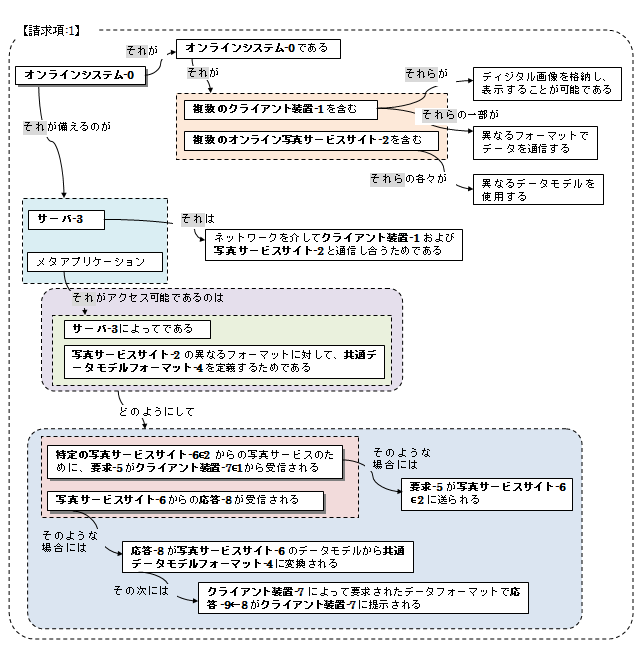
D. 請求項文を英訳する
D.1 和文構造化クレームを英文構造化クレームに翻訳する
↓(和文構造化クレームの構造を保存し、構成要素を英訳していく)